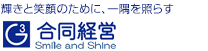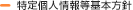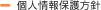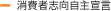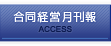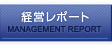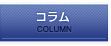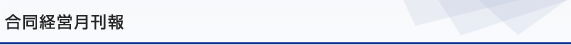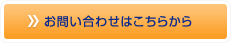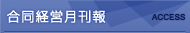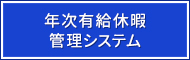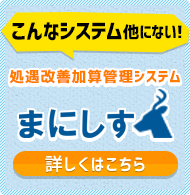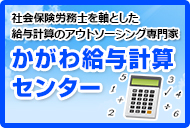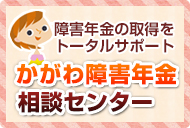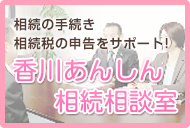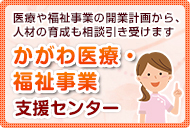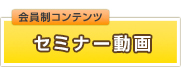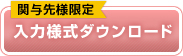令和6年6月からの給与計算に注意!定額減税とは?
令和6年度税制改正の大綱では、令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。その際に給与の支払者が行う定額減税のための事務には、「月次減税事務」と「年調減税事務」があります。今回は、「月次減税事務」について説明します。
月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から「月次減税額」を控除します。「月次減税額」は、控除対象者本人30,000円、同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者)1人につき30,000円の合計金額のことです。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
月次減税事務の流れ
- 1.控除対象者の確認
- 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者かつ令和6年の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人を選び出します。
※各人別控除事績簿の作成
選び出した控除対象者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理するために作成します。国税庁HPに「各人別控除事績簿」が掲載されていますのでご活用ください。
各人別控除事績簿の作成は、義務ではありません。
- 2.月次減税額の計算
-
控除対象者ごとの月次減税額は、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限る。)の人数を確認して計算します。
※同一生計配偶者は、令和6年の所得の見積額が48万円以下かどうかで判断します。
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます。
- 3.給与等支払時の控除
- 令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき所得税及び復興特別所得税の相当額から順次控除します。
- 4.控除後の事務
- 給与等の支払いの際に従業員の方へ交付する給与支払明細書には、適宜の箇所に月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税(所得税)○○円」などと表示します。
事務負担を減らすため、月次で減税対応せず年末調整時に一括減税を行うことは、原則認められていません。そのため、月次減税事務開始に向けて早めに準備を行い、分からないことがありましたら国税庁の定額減税特設サイトをご覧になるか、税理士法人合同経営までご相談ください。
令和6年10月からの社会保険の適用拡大について
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっております。
この短時間労働者の加入要件が更に拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
該当する社員に今後の働き方について、面談をして準備を進めていきましょう。
加入対象(短時間労働者)の要件は?
被保険者数51人以上の企業等(特定適用事業所)に勤務する以下の条件に全て該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない