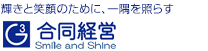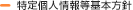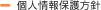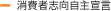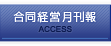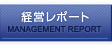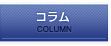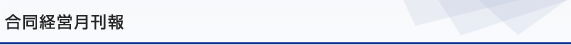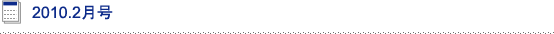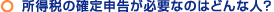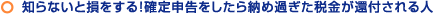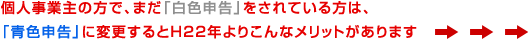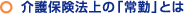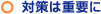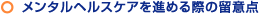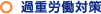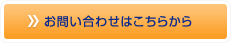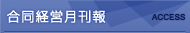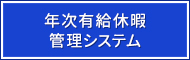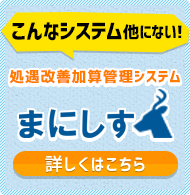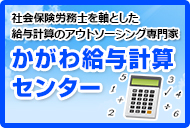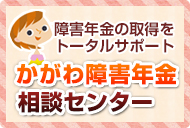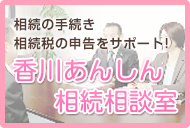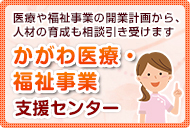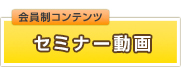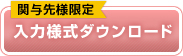確定申告の季節です
所得税の確定申告の時期になりました。申告期間は2/16~3/15です。(還付申告する方はすでに受付中です)個人事業主の方は、正しい記帳を行い1年間の決算書を作成し、早めに確定申告を行いましょう。
- 給与所得がある人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与を受けている人
- 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)が20万円を超える人
- 同族会社の役員や親族で、給与の他に貸付金の利子、店舗などの賃貸料を受けた人
- 公的年金等の雑所得だけの人
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人
など。
- 年末調整後、21年中に子供が産まれたり、結婚した人
- 21年中に住宅を取得して、金融機関からの借入がある人
- 年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人
- 雑損控除(災害・盗難・横領)、医療費控除又は寄付金控除などの適用を受けることができる人
など。
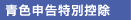
- 複式簿記による記帳を行い、必要な書類を作成し申告期限内に申告する等の条件が揃えば、事業所得(利益)から65万円も控除する事ができます。
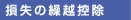
- 損失(赤字)がある場合、翌年以降3年間その損失を繰越す事ができます。
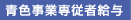
- 税務署に必要な書類を提出する事により、配偶者などの同一生計親族に支払った給与を「専従者給与」として経費に計上できます。(但し適正な額に限ります)
- 他にも貸倒引当金を計上したり、少額減価償却資産(30万円未満)を購入した年に一括で経費に計上する事ができる等があります。
複式簿記で正しい記帳をすることにより、事業の業績が明確になり、経営状況を容易に把握する事ができます。
来年は是非「青色申告」とお考えの事業主のかたは、3/15までに手続きを行いましょう。
介護事業所の皆様 勤務表の組み方は適切にできていますか?
最近は、香川県の監査の際に、就業規則に沿った従業員の勤務表が作成できているかどうかを指導されたという声をよく聞きます。高松市が指導している、常勤の考え方についてご紹介します。
介護保険上で言う常勤者とは、給与形態等によるものではなく勤務時間によります。「介護保険報酬の解釈」によると、常勤か非常勤かは「就業規則の範囲内で勤務した時間数の最大値に達しているかどうかで判断する」とされています。
つまり、月給者で平均週40時間働いていても、月によっては勤務時間が少し足りず非常勤扱いになる場合があると言うことです。
正職員であっても労務管理の仕方で常勤者と認められないケースがおこります。
下記の場合は、夜勤の勤務時間を始業時間の属する日の労働時間としてカウントし、月末に夜勤に入ったCさんは1月の勤務時間の上限177時間を越えてしまいました。その場合は、残業手当等が発生するだけでなく、就業規則の範囲内での上限時間には該当しなくなります。
ですから、AさんDさんの176時間が上限時間になります。Bさんは、176時間に達していないため介護保険上では非常勤になります。
正職員全員を常勤にするためには、毎月労働時間が同じになるように勤務表を作成する必要があります。
常勤であるか非常勤であるかは、常勤者の割合に影響を及ぼしますので、サービス提供強化加算(Ⅱ)を算定できなくなる可能性がありますので、特に注意が必要です。
例)
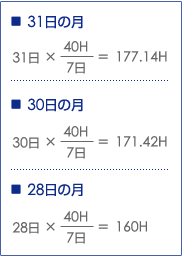
| 氏名 | 雇用形態 | 給与形態 | 1月の勤務時間の合計 | 常勤・非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん | 正職員 | 月給 | 176時間 | 常勤 |
| Bさん | 正職員 | 月給 | 168時間 | 非常勤 |
| Cさん | 正職員 | 月給 | 184時間 | 常勤 |
| Dさん | パート | 時間給 | 176時間 | 常勤 |
| Eさん | パート | 時間給 | 104時間 | 非常勤 |
職場におけるメンタルヘルス・過重労働対策について
仕事上のストレスなどによってうつ病を発症したり、最悪の場合自殺に至るケースも少なくありません。労働者が安心して働ける職場環境を確立ための対策が大切です。
近年では、職場で労働者のメンタルヘルス対策(心の健康づくり)に取り組むことも重要となっています。 また、過重労働対策は、長時間労働などの過重な業務に従事することにより、脳・心臓疾患(脳出血などの脳血管疾患及び心筋梗塞などの虚血性心疾患等)が発症する事がないように、種々の対策を講じるものです。
心の健康については、プライバシーの保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要です。また、人事労務管理と関連する要因によって影響を受けるため、人事労務関連と連携する必要があります。
家庭・個人生活など職場以外の問題を抱えている場合もあるので注意が必要です。
また、メンタルヘルス指針では具体的進め方として以下の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要だとされています。
| セルフケア | 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減あるいはこれに対処する |
|---|---|
| ラインによるケア | 労働者と日常的に接する管理監督者が心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う |
| 事業場内産業保健スタッフによるケア | 事業場内の健康管理の担当者が事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援する |
| 事業場外資源によるケア | 事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける |
労働時間評価の目安と脳・心臓疾患発症の因果関係
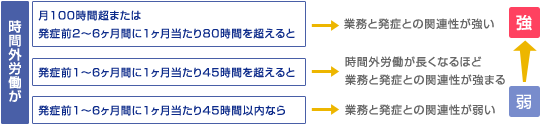
前述のとおり、慢性的な長時間労働が続くと、疲労が蓄積して脳・心臓疾患などを発症する危険が高まるという医学的知見も得られています。
そこで厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合政策」を策定しました。
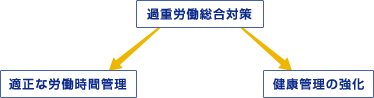
- ①36協定は限度基準に適合するように定める
- ②労働時間は適正に把握する
- ③年次有給休暇の取得を促進する
- ④労働時間等の設定を改善する
- ①健康管理体制を整備する
- ②健康診断を実施し、アフターフォローを行う
- ③長時間労働者等に対して面接指導等を実施する